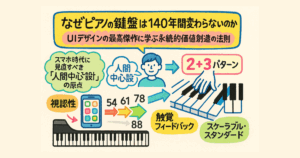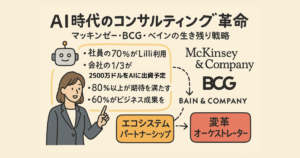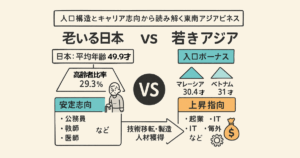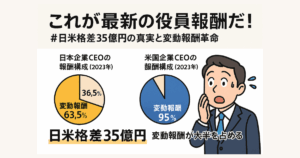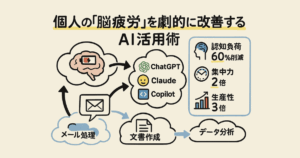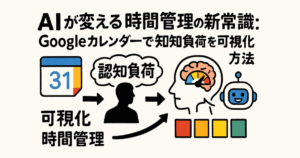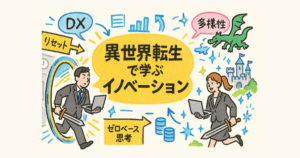「わずか20分前」の警報では遅すぎた
2024年末から2025年初頭にかけて、アメリカ中西部を中心に発生した一連の竜巻群は、27人以上の死者を出し、数百の住宅・商業施設を一瞬で瓦礫に変えた。ノースカロライナ州、アーカンソー州、インディアナ州では非常事態宣言が発令され、保険会社の試算によれば被害総額は約10億ドル(約1,500億円)に達すると見込まれている。
なかでも注目を集めたのは、イリノイ州ロックフォード郊外の中規模製造業での事例だ。竜巻接近の警報が出たのは、実際に建屋が崩壊する20分前。工場長がマニュアルに従い避難指示を出したが、現場作業員の一部は設備の停止作業を優先し、全員避難が完了しないまま竜巻が直撃。3名が死亡、8名が負傷した。
BCP(事業継続計画)が整備されていたにも関わらず、なぜ被害は防げなかったのか?そこには、マニュアルではカバーしきれない“現場判断”の罠が潜んでいた──。
背景:自然災害の「非連続性」がBCPを無力化する
BCPとは、災害・パンデミック・テロといった突発事態においても事業活動を中断させず、または迅速に回復させるための戦略計画である。だがBCPは「起きるかもしれない未来」を想定する性質上、“過去に起きた災害の延長線”という思考から逃れにくい。
米国では、年間平均1,000件を超える竜巻が発生するが、2024年末からのものは異例だった。1つ目は発生回数が突出していたこと。2024年12月だけで178件(NOAA調べ)は、過去30年平均の3倍だ。2つ目はその広がり。これまで比較的安全圏とされてきた州までもが被災エリアとなり、「従来のリスクマップ」が意味をなさなくなった。
そして3つ目が、竜巻の“滞留性”だ。通常なら数分で移動するはずの竜巻が、15分以上ほぼ同一地点で旋回し、局地的に甚大な被害をもたらした。これは近年、地球温暖化と上空のジェット気流の乱れによる「竜巻の性質変化」が指摘されている中で、BCPの前提自体が大きく揺らぎ始めている証左といえる。
教訓1:「設備を守るか、人命を守るか」の選択に答えはあるか
先述のイリノイ州の工場では、「安全第一」の原則が形骸化していた。BCPの中で避難手順は定められていたものの、現場では「まずはラインを止めろ」「装置のシャットダウンを」といった指示が飛び交い、避難が遅れた。
調査によれば、工場の責任者は「設備損壊による操業停止が数週間続けば、契約違反で数百万ドルの損失が出る」と証言しており、リスク回避よりも損益回避が優先された構造が浮き彫りになった。
BCPにおいては「人命優先」は基本原則だが、実際の運用では“現場判断”が経済合理性をもとにブレやすい。このような判断が求められる瞬間においてこそ、マニュアルではなく「行動原則(バリュー)」の定着が問われる。
示唆:BCPはプロセス設計ではなく、価値観の設計でなければならない。
教訓2:「指揮命令系統」は災害時に崩れる
もう一つの事例は、オクラホマ州の地域銀行におけるBCP実行失敗だ。同州タルサにある支店では、災害時対応チームのリーダーが不在のまま突発的な竜巻に遭遇。現場では代行責任者が誰か不明確で、顧客対応と避難誘導が混在。最終的に従業員の1名が取り残されて重傷を負った。
このように「災害時は誰が責任者なのか」という明確化がされていない組織では、緊急時に判断が分散され、行動が遅れる。指揮命令系統の混乱は情報伝達の遅延を生み、結果として人的被害に直結する。
BCPの多くは、計画書やフローチャートに頼りすぎており、実際の「リーダーシップ・シミュレーション」が欠けている。責任者が不在、または通信が途絶した状況でも、誰が代行するのか、どの権限まで行使できるのかという“災害時指揮権限の可視化”は、BCP運用における死角の一つだ。
教訓3:テック化の波が「無意識の依存」を招く
近年はBCPツールも高度化し、クラウド型ダッシュボードやAI予測ツール、緊急通報アプリなどが導入されている。だが、今回の竜巻ではこうしたテクノロジーが「停電」によって軒並み無力化された。
特にIoT化が進んだ物流センターでは、電力網と通信網が断たれることで全てのアラートが遮断され、避難誘導が完全に“人力”に逆戻りする場面が多発した。現地消防局の報告によれば「従業員の多くが“停電=アプリが落ちる”という発想を持っておらず、手動での連絡や避難の声かけが想定されていなかった」という。
災害時のBCP設計において、「すべてがオフラインになる前提」の二重構造が必要だ。テクノロジーの利便性に頼るほど、人間の“初動力”は低下する。特にスタートアップやSaaS企業では、「テクノロジー自体が脆弱性を持ちうる」という視点を持つ必要がある。
具体例:Walmartが導入した“二重BCP”の先進事例
一方で、優れた対策例も存在する。米小売大手Walmartは、近年のハリケーンや暴動、パンデミックで培ったBCPを進化させ、物理災害用とデジタル障害用の「二重BCP構造」を全拠点で導入している。
特筆すべきは、オフライン時の対応速度だ。Walmartでは、電力喪失時にも自動で稼働する蓄電型アラート装置を全店舗に配備。さらに、災害発生時の代行責任者を複数指定し、日常業務とは異なる「災害時チーム」が独立して指揮を執る体制にしている。
その結果、2025年1月の竜巻発生時には、イリノイ州内の3店舗で早期閉店→全顧客避難→スタッフ全員無傷という迅速な対応が実現された。これは「行動設計」と「権限移譲」がセットで運用されていた成果だ。
結論:あなたのBCPは、机上の空論になっていないか?
死者27人を出した米中西部の竜巻は、BCPの存在そのものを問う災害だった。計画書があることと、それが“現場で機能すること”の間には大きな乖離がある。
本稿が示した3つの盲点──
- 人命より設備を優先する判断構造
- 指揮系統の不備による初動遅延
- テクノロジー依存の脆弱性
──はいずれも「計画を運用する人間の行動」に帰結する。つまり、BCPは「設計」以上に「習慣」や「文化」の領域に踏み込まなければ機能しない。
読者のあなたが、もし経営者・責任者の立場であるならば、今一度問いたい。
「その計画は、災害時に人を動かせる設計になっているか?」
それが、次の災害への備えの第一歩である。